「先生シリーズ」として有名なシリーズですね。
わたしもずっと以前から何となく耳(目)にしていて、興味持っていました。
まずこのタイトルにかなりそそられませんか。
どなたかがレビューで書いておられましたがこのシリーズは
「安定の面白さ」
軽妙洒脱、ユーモアたっぷりの語り口で、小林先生が鳥取環境大学の「日常」を通して、あふれる動物愛研究愛を綴られています。
楽しく読めて心温まりつつ、時々ちょっと考えさせるところもあるこのシリーズ、人気もさもありなん。
各エピソードもやや短めで分量としてもほどよく、忙しい方でも負担にならずに読めるところもポイントでしょうか。
面白いです!
かくも動物愛な人々

このシリーズはサブタイトルに「[鳥取環境大学]の森の人間動物行動学」とあるように、鳥取環境大学で実際に起こった「事件」の数々を鳥取環境大学環境学部環境学科の小林教授(専攻:動物行動学・人間比較行動学)が著したものです。
鳥取環境大学では実際に、たまにコウモリが廊下を飛ぶらしいです。
表題の「先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!」が2007年に出版されて以来同シリーズは、概ね年1回の刊行を続け、2025年10月時点で20冊ほどとなっています。
あら10月下旬には新刊が出るんですね。
小林先生と学生たちの「日常」はたとえばこんな感じです。
(以下「先生、巨大コウモリが・・・」から引用)
私に近寄ってきたIくんが話をはじめた。
本書より
「さっき先生にメールしたんですが、巨大なコウモリが一階のドアの内側で飛びまわっていて、天井の隙間に入りました」
巨大なコウモリが侵入したか。・・・・・・すばらしい。
Iくんは、私の顔が一瞬輝くのに気づいただろうか。川での作業で疲れていた体に力がよみがえるのを感じた。これは開学五年目にして初の事件だ。
私は何を隠そう、大学の研究室でヘビを飼育している。
本書より
(この告白で、私は大学の中でさらに孤立するだろう。それでなくても、私の向かいの部屋の、ある法律の先生は、私の部屋のことをアナザーワールドと言って近寄られない。きれいな女性の先生であるが、見事な直感というほかない。)
先生は、アリが巣をかまえている木の化石を研究室に持ち帰り、巣のそばに水と食べ物の入ったシャーレをわざと石から少し離して置きますが、それはアリの運動不足を懸念したのに加え、
巣を出て、餌を求めて歩き回るというアリ本来の生態を机の上の空間で実現させたかった
本書より
俗っぽく言うと机の上の少し広い空間を、アリたちの生態小宇宙にしたかった
本書より
ため。
大学林で作業をしていてアオダイショウに出会っても、小林先生の身体は反射的に動いてしまいます。
おいおい、捕まえてどうするんだ。飼うのも面倒だろ。
本書より
そんな「内なる声」もなんのその、そう思った時にはもう小林先生の足はヘビのしっぽを踏みつけ、
なかなか元気のいい、きりりとしたかわいい顔のオス
本書より
を袋に入れザックに納めてしまいます。
先生の研究室にはヘビ以外にもいろいろな動物が飼われており
気を緩めると動物が増えていくのでいつも気をつけている
本書より
ものの、学生の皆さんは動物を捕獲しては
「小林が喜ぶだろうと持ってきてくれ」たりするのです。
学生のみんなも動物愛は筋金入り。
愛用のたも網を巧みに使うTくん、シカの研究のため「大した行動力」でボートや必要機材を用意し湖上の小島に通いはじめるKくん。
先生の部屋では「温かい珈琲をすすりながらイモリやヤツメウナギの話で盛り上がり」、ヤギ部を結成して学内でヤギを飼い、先生が「田んぼの稲に被害を与えるイノシシの捕獲に挑戦しよう!」というテーマを掲げれば面白そうだと希望する学生たち。
タヌキの移動ルートを調べるためGPSを取り付けたタヌキを離した時。
タヌキの位置をパソコンでチェックするたびに、GPSの契約料とは別に、一回につき100円の料金が加算されるため、各人の担当時間を決め、自分の担当以外の時間帯ではチェックは我慢する取り決めになったのですが
月初めに届いた請求書には驚いた。
使用料が高額なのである。
学生たちが誘惑に負けて、自分の担当以外の時間帯にもパソコンをチェックしたからだ。
(中略)
おそらく学生たちは、「一回ぐらいなら」とパソコンの中のコバキチに会いに行き、一回が二回に、二回が三回に・・・なのだろう。
本文より
という結果。
しかし、寛大な私は彼らを責めようとは思わなかった。というのも、私も何度も誘惑に負けて、夜な夜なパソコンの中のコバキチに会いに行ったからである。
本文より
仕方ありません。払いましょう。
シリーズ二冊目の「先生、シマリスがヘビの頭をかじっています!」も一冊目同様の内容ですが、こちらのほうが「巨大コウモリ・・・」よりもより、動物の生態事例が多いようです。(「生態事例」と言うより「先生と動物たちの間に起こったドラマ事例」と言うべきか。)
こちらの読後には、一冊目よりなお強く、
「なんか、ためになったなあ」
「野生動物ってこんなに面白いんだ」
と感じていました。
先生は「バイオフィリア」

小林先生はご自身のXアカウントのプロフィールに、
野生生物と3日ふれあわないと体調が悪くなる動物行動学者
と記しておられます。
本書に書かれているのですが、アメリカの生物学者ウィルソンは、人間の、生物や生物同士が作り出すさまざまな関係に魅了される生得的な心理特性をバイオフィリアと名付けました。
ハサミムシとダンゴムシのやりとりにひきつけられる私は、もう“バイオフィリア”が服を着て歩いているようなものである。
本文より
アリが巣から出て周囲を探索する様子、アリが机の上の水滴を飲む様子、アリが仲間同士で触覚をふれあわせる様子など、見ていてワクワクするし、これまで見たこともないような行動出くわしたときなど、“背中がぞくぞくするような”感覚を覚えることがある。ウィルソンのいう“ナチュラリストの恍惚”に近いものである。
本文より
なるほど、そういう感じなんだ。
完全に理解はしていないかもしれませんが、そう書かれると少し気持ちがわかる気がしてきました。そして自分も、今後それに近いようなかたちで、動物(含昆虫)を見ることができるような気持ちもしてきたのです。
小林先生の、愛情に裏打ちされた観察眼およびその記録は、いわゆる「動物観察」「生態調査記録」とはかなり違うと感じました。たとえば今までテレビの動物番組や動物観察番組を見て、これほど興味を惹かれたことはなかったからです(そういう番組を否定するものではありませんが)。
先生のユーモラスな筆致がそう思うのかなとも考えましたが、どうもそれだけではない気がします。
「違う」と感じる要因の1つは、小林先生の目線の位置にあるのではないでしょうか。
小林先生が動物を見るまなざしは、自らと対象の間に段差を置く「調査」「観察」ではなく、あくまで同じ立ち位置に立った目線からの観察のようです。
読みながらその立ち位置に自分も立った時、動物を見る新たな視点がわたしにも見えてきたように思うのです。
そしてその一方で小林先生はある種の「動物好き」ともやはり違う印象を受けます。
動物大好き!いろんな動物と暮らしたい!それは先生もそうなのですが、なんだかちょっと「違う」感じがする。動物と「同じ高さ」にいながら「べったり」にはならない。
この、動物との絶妙な「距離感」が小林先生の著書の魅力の1つかもしれません。
愛が興味を呼ぶのか、興味が愛を誘うのか?ある対象を「知りたい」と思うことも1つの縁。「知りたい」という気持ちの中にはたとえ微量であっても「愛」は存在し、また知れば知るほど愛が深まっていったりする。
人間関係では必ずしもそうでもないのかもしれませんが(笑)、「知る」というのはやはりかなり大切だなあと思います。
「動物好き」の方はきっと大いに共感し、「動物好き」ではなかった人には新しい世界を見せてくれる本。
まあそんな定義付けはともかく、
掛け値なしに面白い本
だと思います。
現時点でまだ二冊しか読んでいないのですが、他のご本も全部読むぞ!とこれは心に決めていますよ。


Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
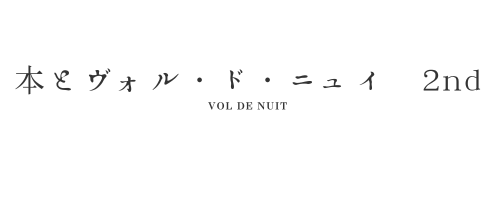
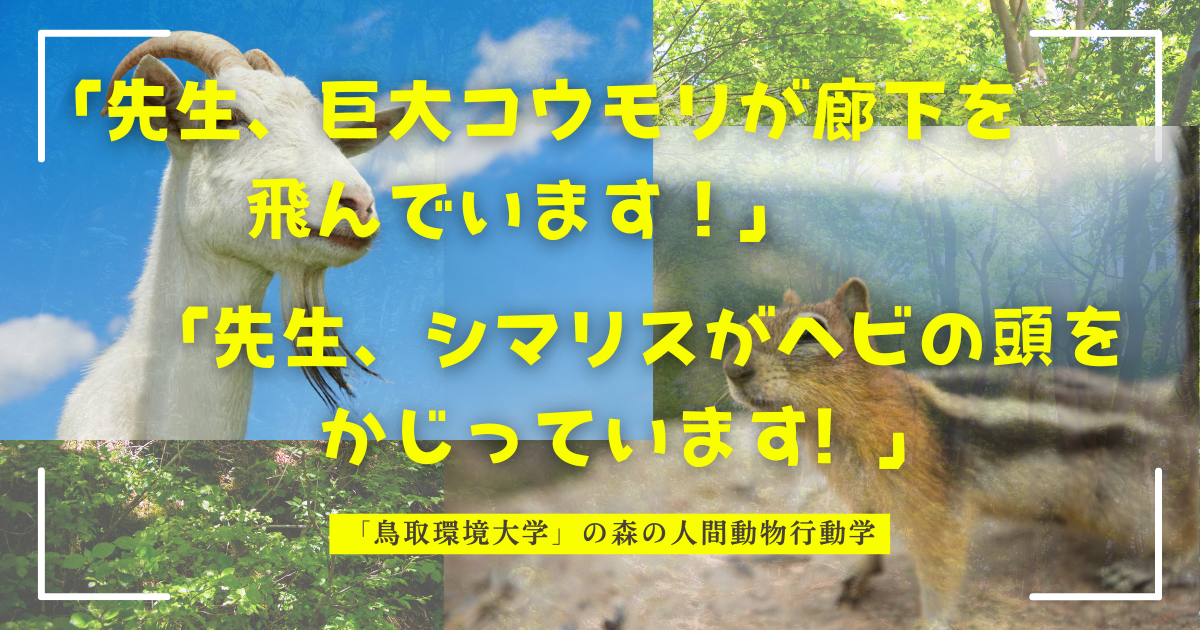

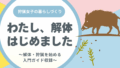
Comment